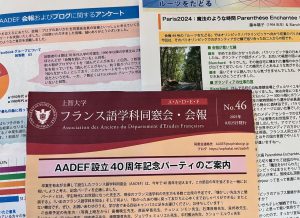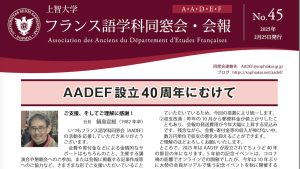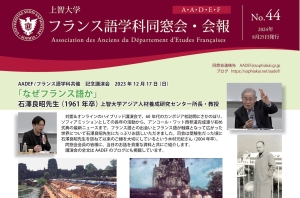◆ 大きな仕事を可能にする土台は?
あらためて考えてみると、私の仕事は多岐に渡っている。美術史や展覧会についての専門的な知識、企画を実現させるための推進力とノウハウ(そこに語学力も含まれるのだろう)、そして日本と欧米諸外国の美術界におけるネットワーク。こうした専門性、実務調整力、情報収集力などが長い経験のおかげで自然に身についたと近年は特に感じている。
上智大学を卒業して1983年4月、私は読売新聞社に入社した。当時はまだ男女雇用機会均等法が制定される前で、就職試験で女性は新聞記者職での募集だった。大学時代から美術・音楽に関心があり文化関係の仕事に就きたかったが、男性と同じ給与・昇進となると選択肢は非常に限られていた時代だ。私は将来の希望として新聞社の文化部を希望していたのだが、面接試験が終了したところで「実は今年は、記者職だけでなく、広告局と事業局に一人ずつ女性を配属することになった。文化事業部という西洋美術の展覧会を開催する部署がある。あなたは文化に関心があるようだし、外国語を必要とするのでどうだろうか」という話をいただいた。こうして文化事業部に配属され、主に西洋美術展の担当となった。入社3年目の1985年10月、パリ支局駐在を拝命する。当時110周年を迎えた読売新聞社で初めての女性の海外支局駐在員だった。通例では数年後に日本に戻るところ、私はパリに残ることを選択し、現在はフリーランスとしてこの仕事を続けている。

切り紙絵の大作『花と果実』の展示風景
パリに残った最大の理由は南條彰宏との結婚だった。南條は、日本の美術展史に残る「バー ンズ・コレクション展」(1994年、国立西洋美術館)を仕込むなど、1960年代から2000年代初頭まで数々の展覧会を手がけたこの道の先人であった(南條のことはいずれ別の機会にまとめたいと思っている)。彼のそばにいて見聞し学んだことは、代え難い私の財産となっている。
どうしたら私のような仕事に就けるのか、と問われるのが実は答えに一番困る。運良く自分の気質に合っている仕事に巡りあい、目の前の一つ一つのプロジェクトを丁寧に手がけることを心がけてきた結果だと思っている。継続してこられたのは、私を必要としてくれる仲間がいるからだし、また、自分のことで言えば、関心と情熱を持ち続けている分野なので楽しみながら続けられたからだろう。立場上、入場者数の見込める(人はそれを “ブロックバスター”と言う)展覧会を企画することが私に求められていると理解しているが、現代美術、音楽やバレエも鑑賞するし、ファッションや美味しいものを食べることも大好きだ。フランスのプレスカードを持っていて、これまで新聞、雑誌に寄稿も続けてきた。取材をしたことが、展覧会の仕事に形を変えてつながったことも多い。