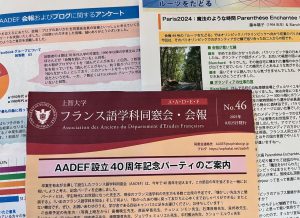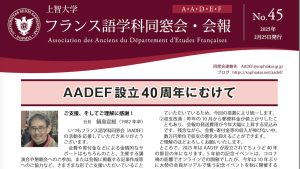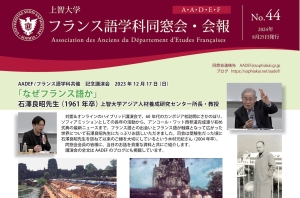日本は現代社会で孤立する人や相対的貧困者が増え、精神をわずらう人も増えています。しかし、セネガルをはじめとする西アフリカでは大家族が当たり前で、困った人がいれば助け合うのが自然ですから、そういう問題が殆どないのです。私も、セネガルでは義母たちと何十人分もの食事を大鍋で作ります。セネガルは、文明の現代化も盲目的に受け入れているわけではないんです。スプーンを使わず手で(独特の美しいテクニックがあります)、大皿料理を食べることが今でも珍しくありません。

それで炭火でゆっくり沸かしたミントティーを飲んで、広い中庭でみんなで延々と喋っています。私が初めて訪れた20年前と比べて、中産階級は増え、ビジネスで成功している人も続々と生まれていますが、人々の日常生活はほとんど変わっていないのが魅力的なところです。
アフリカの人々と話していると、祖父母から孫まで一緒に暮らす大家族が多く、歴史が繋がっているように感じます。彼らは「個人の幸せ」よりも「家族の幸せ」を大切にし、何か悩みがあっても一人で抱え込まず、周りに人がいてくれる。悩みを話し始めるとずっと聞いてくれるんです。日本の今の流行り言葉でいう傾聴ですよね。それで話終わると「それはあなたの問題じゃない」というような反応で、相談した方も肚落ちしていくんです。日本社会で「精神科や心療内科が増えた」と感じる一方で、アフリカには「自浄作用」のようなものがあり、悶々と悩むような環境ではない。そこは日本が学べる点だと思います。
東日本大震災の際に日本で話題になった「お互い助け合い」の精神、おそらく昔の日本には、そういう精神が根付いていたのだと思いますが。それが、アフリカでは今も日常的に実践されているんです。また、繰り返しになりますが、日本では「こども食堂」が必要とされていますが、セネガルでは困っていてもいなくても、近くに子供がいたら「うちで食べなさい」となる。料理を普段から多めに作り、突然の来訪者に備えているのです。人間関係の豊かさを強く感じますね。