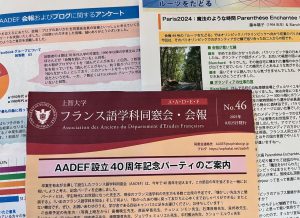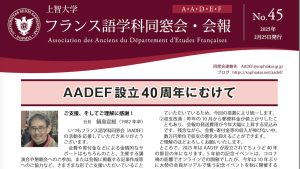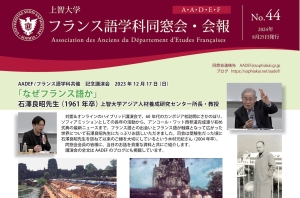ただ、貴賓としてもてなすわけでないんです。日本だと、お客さんを迎えるのに、掃除したり準備が大変ですよね。セネガル人の夫と話していて、そこまでしなくて良い、大切なのは人と過ごす時間なのだと思うようになりました。
◆ フランス語圏アフリカの現状と、日本との今後の関係性についてどうお考えですか?
この20年、日々の暮らしはあまり変わらないと話しましたが、地政学という意味では大きく変わっています。フランス語圏アフリカでは、フランスの影響力が徐々に低下し、ブルキナファソやニジェール、マリのようにロシアとの関係を強める国も出てきています。フランスがアフリカで最初の植民地にしたセネガルでもフランス離れが起きていますし、第二のパリといわれるアビジャンがあるコートジボワールも緩やかにフランスから離れていくのではないでしょうか。そして、かつてベルギー国王が統治したコンゴ民主共和国は資源国ゆえに、先進国の利害に翻弄されているように見えます。アフリカだけではないかもしれませんが、資源を持っているがゆえに、他国からの干渉で安定しない国が、世界には少なからずあります。
今、サブサハラで経済成長をけん引しているのは、ナイジェリア、ケニア、ガーナといった英語圏です。背景を考えるうえで、知っておいてほしいのは、
「フランサフリックFrançafrique」という表現です。独立後も続いていたフランスと旧アフリカ植民地の指導者との間の緊密な関係のことです。歴史を辿ると、アフリカを支配するために、フランスが背面で現地の政治をマニュプレートした疑念が拭えないわけです。イギリス帝国主義は地方分権でしたが、フランス帝国主義は中央集権でしたので、尚更、中央から統治したいという願望があったのかもしれません。しかし、歴史的にフランス語で思考してきた彼らの考え方が急に変わるとは思えません。
中国の影響も無視できません。人もお金もアフリカに投入していて、一部の国では、中国からの債務が返せず問題になっています。私が駐在していたマダガスカルでも、
中国の影響力は大きくなっています。
そんな中で、欧州がアフリカへの援助疲れしていた1990年代に日本が始めたTICAD(アフリカ開発会議)は派手さはありませんが、アフリカとの関係を持続的にする有意義な活動だと思います。